この記事で言いたいこと
- 定期的な健診の受診が大事
- 40歳以降は、健診にあわせて脳のMRIも撮っておくべし
なぜ書くのか
このブログを以前から知らせているような間柄の誰に話していて、誰に話していなかったかよくわからなくなるのでここに記しておきます。
または、「聴神経腫瘍(または前庭神経鞘腫)」というキーワードで体験記を探してきた誰かのために。
時系列が新しいものから書いていきます
同じ症例を患って体験期を探している方は、「前兆」や「どのように発覚したか」よりも、「どのような治療を行ったか」「入院や治療はどんな体験だったか」を求められているでしょうから、時系列が新しい事柄を先に書くようにしますね。
ただし、入院生活の1日目・2日目・3日目については時系列順に書いています。
退院直後にこの記事を書き始めています
2025年10月上旬に、聴神経腫瘍(前庭神経鞘腫)の治療のために入院しました。
詳しくは後述しますが、私は開頭手術による物理的な切除ではなく、「ガンマナイフ治療」という開頭を要しない放射線治療を選択しました。
この体験期を書いているのは退院して間もなくの時期ですが、日常会話や一般的な音楽鑑賞は治療前と遜色ない……と思っていたところ、職場で鳴らされるチャイムや呼び出しのベルの音が、半音ほど低く聞こえるという自覚症状があります。
これが一過性のもので、今回の治療によって徐々に腫瘍が小さくなれば元に戻るのか、それとも特定の音だけはずっとこのままの聞こえ方なのかはわかりません。
また、頭痛ともちょっと違う感じの不快感というか不安定感があり、長時間立つというのは少し辛い状態でもあります。
入院生活1日目
病院によって若干の差異があるかもしれませんが、私がお世話になった病院では「1日目に入院の諸手続きと簡単な検査」「2日目にガンマナイフ治療本番」「3日目に退院の諸手続き」という2泊3日の日程でした。
1日目の検査は身長・体重の測定、熱発していないか・COVID-19に感染していないかの検査、血液検査といった簡単なものです。
諸手続きと検査が終わればほぼ自由時間で、昼食・夕食も病院の通常食をいただきました。
ただし、21時以降は絶食とされ、水分以外は摂らないよう指導されます。
理由を尋ねたところ、「長時間仰向けで治療を受けることになり、また体質によっては吐き気を催すこともあるため、胃の中に何もない状態にしてもらう」ということでした。
入院生活2日目
2日目、これは病棟の入院患者とスタッフ数のバランスの関係もあって早めに対応したそうですが、6時台の早いタイミングで術衣に着替え、MRIを撮影するため指輪等の金属類を外し、手の甲から造影剤や他の薬剤を輸液するための点滴針を穿刺しました。
前述のとおり昨夜21:00から絶食を継続しているため朝食は摂らず、8:30の治療フロア移動までは少し病室で待機する時間がありました。
体験記を探して来られた方は既にお調べになっているかと思いますが、ガンマナイフ治療というのは腫瘍部位に集中して放射線を照射する治療のため、治療の最中に患者が頭部を動かしてしまう、ということがあってはいけません。
そのため、金属製のフレームを頭部に装着し、治療中はガンマナイフの機器に固定するという形式をとります。
また、完全な麻酔ではありませんが、眠気を誘発するような薬を用いて不用意に体を動かさないようにもするとのこと。
治療フロアに移動後にそのフレームを装着し、まずは治療計画(照射部位)を確定させるためのMRI検査・CT検査を行います。
それらの検査が終わるといったん病室に戻され、撮影したMRIとCT画像で正確な腫瘍位置を見定めて、治療機器にガンマ線の照射位置情報をインプットするそうです。
MRI検査・CT検査の際は眠気を誘発する薬は少量だったのかもしれませんが、その後に迎えた本番の治療ではしっかりと薬が効いており、「麻酔ではないので「一瞬で終わった」ということではなかったけど、時間や場所の感覚があやふや」という感じで、最中の記憶がおぼろげです。
ちなみに治療フロアから病室に戻る際は車いすで運んでいただきましたが、病室に戻ってベッドに移動する際にはスタッフの手を借りつつも自分の足で上がることはできました。
開頭手術ではなくメスを入れるわけではないとはいえ、「放射線治療」というものもまったく体に負担がないわけではありません。
この「ベッドに戻った直後」は、これまでに経験したことがない強さの頭痛に襲われました。
13時少し前にベッドに戻ったため、昼食は配膳いただいたのですがとても食事どころではありません。
(同じ病室に、症状は少し違えど同じガンマナイフ治療の患者さんがいましたが、その方は私の後に治療を行うタイミングだったために昼食も抜きだったようです)
あらかじめ「苦痛に耐えられぬ時のむがいい」と渡されていた鎮痛剤(アセトアミノフェン)を飲み、30分ほど耐えたところで鎮痛剤が効き始めたため、なんとか昼食をとり終えることができました。
その後少し横になって休んで過ごし、点滴針を抜いて頭の包帯を外して……と徐々に身軽になっていきます。
そうそう、包帯が急に登場しましたが、先ほど「金属製のフレームを頭部に装着」とサラッと書いた際に、ボルトのようなものでガッチリと固定されるため、こめかみのあたりと後頭部に出血を伴う程度の傷はできます。なので頭に包帯が巻かれていました。
このように頭部に傷があるため入浴はできませんが、夕食時には頭痛も治まって通常通りの食事ができ、就寝への流れで2日目は終了しました。
入院生活3日目
3日目は特に治療や検査に関する事項はなく、退院に向けた手続きのみです。
2日目の時点で頭の包帯を外していたため、後頭部の傷から若干の出血があっており、枕に敷いていたタオルは血液で汚れていました。
ちなみにこめかみの方の傷は5日間ほど絆創膏で保護するようになっているため、そちらからの出血は服を汚したりしてしまう、ということは特にありません。
退院後は入浴も可能となるため、その都度傷口を消毒して絆創膏を貼りかえるという処置を行っています。
自覚できるような前兆はあったのか?
耳鳴りや難聴、めまいで不調を自覚して病院を受診し、症例が判明するという方もおられるようですが、私の場合は後述する経緯で偶然判明するまでは、まったく自覚症状はありませんでした。
ただし、「今考えるとあの症状は前兆だったのかも……」というもの(突発性難聴)はありましたが、「難聴だから即腫瘍を疑う」ということはまずないようです。
そのため、不調がなくても定期的な健診を受診し、また一定の年齢(40歳以降)になれば脳ドックなどでMRI検査を定期的に受けることをお勧めします。
判明するまでの簡単な経緯
2025年6月にCOVID-19やインフルエンザは陰性だけど高い発熱があり、かかりつけのクリニックで抗生物質を処方いただくもなかなか改善しない……ということがあり、倦怠感や強い眠気も伴っていたため甲状腺なども専門としているクリニックにセカンドオピニオンを頼りました。
そこでの問診や血液検査では「甲状腺による発熱や怠さではないけど、抗体値も高くなっていて普通の風邪とも違うようである」とのことで、念のためMRIを撮っていただくことになり、私にとってはこれが人生で初めてのMRI撮影でした。
そのMRIで、この不調は「副鼻腔炎」によるものが判明したのですが、あわせて「右耳の付近に腫瘍の影が見える」ということで、ここで初めて聴神経腫瘍(前庭神経鞘腫)であることが判明したという流れです。
開頭手術かガンマナイフ治療か
さて、聴神経腫瘍(前庭神経鞘腫)の場合は治療方針が大きく2つに分かれ、開頭手術か「ガンマナイフ治療」を選ぶことになります。
以下に、私が伺った話にてそれぞれの特徴をまとめます(私は医療関係者ではないため、医学的に正確な記述でない可能性があります)。
開頭手術
- 腫瘍を物理的に除去するため、残存させる腫瘍のサイズにもよるが治療効果は高い
- 腫瘍のサイズが大きくなっており、聴神経に癒着している場合もあり、その場合はある程度腫瘍を残存して聴力を温存するか、または聴力の低下・消失を伴ってでも腫瘍の除去を優先するかの判断が必要
この「腫瘍の残存による聴力の温存」と「聴力の低下・消失を伴う腫瘍の除去」は悩ましいところで、私が相談した医師は「開頭手術の場合、聴力の低下は高い確率で起こると認識してほしい」との説明もありました。
ガンマナイフ治療
- 開頭することなく治療可能
- 定位放射線治療によって腫瘍の増殖を抑制する
- 腫瘍のサイズが30mmを超えている場合は放射線障害を避けるため、開頭手術による腫瘍の物理的な除去一択となる
- 5%程度の確率で、腫瘍からの蛋白流出で水頭症などを合併することがあり、その場合はシャント手術で対応する必要がある
- 治療後6ヵ月経過するくらいまでは、一時的に腫瘍のサイズは大きくなることもあるが、以後は縮小していく
- 退院後は経過観察として、3ヵ月ごとのMRI撮影が必要
- 10%程度の確率で、ガンマナイフ治療での腫瘍の増殖抑制に至らない場合がある
ということで、開頭しなくていいのなら即ガンマナイフを選択すればいい、ということではなく、低い確率ではあるものの合併症の発症、または治療効果が得られない可能性はあるとのことでした。
しかし、開頭手術によるデメリットも踏まえて熟考の末、私はガンマナイフ治療を選択しています。

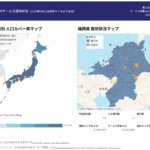
コメント